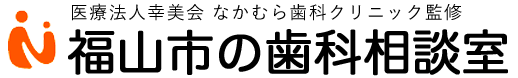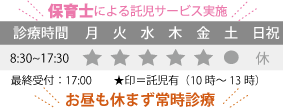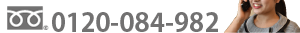歯性感染症の原因は?その兆候(症状)と治療方法

歯や歯茎が痛くなることがあっても、「しばらくすれば落ち着くし」と様子を見ている人もいるかもしれません。
ところが、このような状態をいつまでも放置していると、歯や歯茎だけの問題にとどまらず、全身の問題につながることもあります。
むし歯や歯周病などの感染症が原因となって周囲に感染が広がることを「歯性感染症」と呼びますが、これによって命に関わるほどの重篤な問題に進展してしまうこともあるのです。
今回は、
・歯性感染症とはいったいどのようなものなのか
・歯性感染症の原因とは
・歯性感染症の初期に見られる兆候とはどんなものか
・歯性感染症になった場合どんな治療方法があるのか
ということについてご紹介していきます。
1.歯性感染症とは
1-1口内細菌感染が周囲に広がっていく感染症
むし歯や歯周病は口内細菌が原因で起こる細菌感染症です。
歯性感染症は、このような歯の周囲の細菌感染があごの骨などの周囲組織、そして周囲の臓器や全身に広がっていくことをいいます。
歯性感染症を引き起こす原因は口の中にいる複数の細菌ですが、私たちの口の中には普段から多くの細菌が生息していますし、それだからといって感染症がすぐに発症するわけではありません。
口内に住んでいる常在菌は通常は無害なものですが、何らかの異変が起こって細菌の量や毒の力が増えてしまい、体の抵抗力を上回ってしまうと感染症を引き起こします。
1-2歯性感染症の例
口内の感染症に対して適切な対処を行わないと、感染症が周囲の組織に広がっていくことがあります。
具体的には次のような状態を引き起こす恐れがあります。
◆歯肉の炎症
歯茎の炎症が広がって腫れと痛みが強くなり、ものを飲み込むと痛い、口が開けづらい、顎の下のリンパ節の腫れといった症状が起こります。
◆歯槽骨炎
歯の周囲の炎症が骨にまで広がり、膿を溜めていきます。歯を触ると痛い、歯が動く、といった症状も起こり始め、全身症状として発熱を起こすこともあります。
◆骨膜炎
骨の外側を覆っている膜に炎症が及ぶと、顔、顎の下の広範囲の腫れ、熱感などが現れてきます。痛みも激しくなってきます。
◆骨髄炎
骨髄内に感染による炎症が広がっていくもので、歯肉や顔面の腫れは軽めのことも多いです。
歯の動揺、押すと痛い、強い痛み、発熱などがあり、全身の倦怠感や食欲不振なども発現することがあります。
下顎に起こる場合、顎の下リンパ節の炎症や下唇やあごの先端部付近の知覚過敏やしびれが起こることもあります。
◆蜂窩織炎
感染による炎症が広範囲に広がって浮腫を起こし、組織の間の密度が少なくなることでその隙間をぬって感染が広がっていきます。
舌の下部や頬の部分に多く見られ、赤み、強い痛み、口の開きづらさ、リンパ節の腫れなどが現れ、高熱、倦怠感、食欲不振なども起こります。
ひどい場合には、呼吸困難、肺に膿が溜まる、敗血症といった状態を引き起こして命に関わることもあります。
◆上顎洞炎
上の奥歯の細菌感染を放置していると、その上部にある上顎洞という副鼻腔に感染が及んで、頬の痛み、頭痛や目の痛み、腫れ、鼻づまり、悪臭の鼻汁、歯の浮いた感じや痛み、発熱、倦怠感、食欲不振の症状を起こすことがあります。
2.歯性感染症の原因とは

歯性感染症を引き起こす原因となるのは、主に次のような状況です。
いずれも放置することで感染症が歯の周囲からあごの骨、そして周囲の組織へと広がっていく危険性があります。
2-1 歯根の周囲の膿だまり
むし歯を放置して神経が壊死してしまった、過去に神経を取った歯に細菌感染が起こってしまった、という場合、歯根の周囲の骨を破壊して膿をためる「根尖性歯周炎」を引き起こす原因になります。
2-2重症の歯周病
歯周病は歯周病菌によって歯を支えている組織が破壊されていく病気で、歯茎の出血や腫れといった症状から始まり、次第に炎症による骨の破壊が起こって骨が溶けてしまい、だんだんと歯を支えられなくなっていきます。
歯周病の急性炎症が起こって腫れが出ている時に適切な処置をしないと、周囲に炎症が広がる恐れがあります。
2-3炎症を繰り返している親知らず
親知らず周囲に炎症を起こすことは珍しくありません。
それは、親知らずが奥に位置しているために歯ブラシが届きにくいこと、生え始めてから生え切るまでに時間がかかることが多いこと、まっすぐ生え切らないことが多いこと、といったことが関係しています。
時々起こる多少の炎症はそれほど問題にならないことが多いですが、もし仮に大きく腫れて痛い状況が繰り返し起こっている場合、それを放置していると急性的な激しい炎症が起こり、周囲に感染が一気に進むことがあります。
2-4抵抗力の低下
歯根周囲の膿だまりや歯周病、親知らずの炎症があるからと言って、全ての人が歯性感染症を起こすわけではなく、実際にはどちらかというと稀で、そこまで至らない場合の方が多いと言えます。
ですが、身体の抵抗力が弱ると歯性感染症を起こすリスクが高くなります。
身体の抵抗力が弱まる原因としては、
・疲労
・睡眠不足
・栄養不足
・糖尿病
・糖分の摂り過ぎ
・運動不足
・アルコール、喫煙
・加齢
・腸内環境の悪化
・口内細菌環境の悪化
・ステロイド剤や免疫抑制剤、抗がん剤などの使用
・ウイルス感染
・ストレス
などが挙げられ、こういったことにも注意を払うことが大事です。
3.歯性感染症の初期にみられる兆候とは?
歯性感染症の初期にみられる兆候としては次のような症状が現れます。
・歯や歯茎の痛み、違和感
・歯茎の腫れ
・口臭の悪化
・リンパ節の腫れ
・口の開きづらさ
・飲み込む際の痛み
・発熱
・倦怠感
初期症状とはいえ、歯性感染症は一気に広がることがあるため、油断せずに何かおかしいなと思う症状がある場合には早めに歯科を受診するようにしましょう。
4.歯性感染症の治療方法

歯性感染症を起こしている場合、感染の原因や状態、場所により異なりますが、次のような治療が行われます。
4-1抗生剤の投与
まずは感染による急性的な症状を落ち着かせるために、飲み薬もしくは点滴の抗生剤投与が行われることが多いです。
4-2切開
膿の溜まりが多い場合、切開して出そうな場合には麻酔をして歯茎の切開、膿の排出を行います。
4-3原因歯の治療
症状が落ち着いてきたら、原因歯の治療を行います。
歯根の膿だまりに対しては根の治療、歯周病に対しては歯周病治療、親知らずの場合や、それ以外の歯の場合でも状態があまりにも悪い歯の場合には抜歯を行います。
4-4入院治療
重篤な全身症状を起こしている場合には、大学病院や総合病院に速やかに依頼し、入院して抗生剤の点滴を受けたり、皮膚からの切開をしたり、といったことが必要になってきます。
5.まとめ
歯性感染症は、むし歯や歯周病、問題のある親知らずを放置しないことで防げます。
もし歯性感染症になったとしても、早期の対処により軽症で済み、抗生剤の内服薬で一旦症状が落ち着くことも多いですが、放置すると最悪命に関わることもあるため、早急に歯科を受診するようにしましょう。
なお、一旦応急処置で炎症は落ち着きますが、原因となる歯をそのままにしていると、再度同じ状況が起こるか、細菌があごの骨の中に入りこんで慢性の骨髄炎を起こすと非常に治療が難しくなることもあるため、原因の歯の治療はきちんと受けるようにしましょう。
この記事の監修者

こちらの記事もおすすめ!