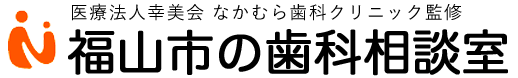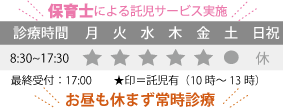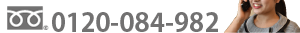「磨いているのに汚い」になってない?プロが教える正しい歯ブラシの使い方と選び方、交換時期について

ひょっとしてその原因は、歯ブラシの仕方に問題があるか、歯ブラシ自体に問題があるのかもしれません。
もし間違った歯ブラシの使い方をしている、もしくは歯ブラシ自体に問題があるのに使い続けている場合、せっかくの歯みがきの努力が水の泡になってしまうだけでなく、歯の健康を損ねてしまう恐れもあります。
そのようなことにならないために、今回は、
- 歯ブラシの正しい使い方
- 自分に合った歯ブラシの選び方
- 歯ブラシの交換時期
について解説します。
歯を一生健康に保つのに大事なのは、やはりなんと言っても毎日の歯ブラシ。
間違った方法で損をすることのないように、ぜひ今回の内容を最後まで読んでみてくださいね。
1.歯ブラシの正しい使い方とは!?
歯ブラシはただゴシゴシ動かせばよい、というものではありません。歯磨きの効果を十分に発揮させるためには、「持ち方」「力加減」「動かし方」「磨く場所」「歯ブラシをするタイミング」などに注意が必要です。
1-1歯ブラシの持ち方
まず、歯ブラシの持ち方はとても大事です。
持ち方によって力の入り具合や動かしやすさが違ってくるからです。
おすすめの持ち方はペングリップ(ペンを持つときの形)です。
この持ち方なら、力が入り過ぎず、適度な力で歯ブラシを細かく動かすことができます。
1-2歯ブラシの力加減
歯ブラシをする時、ゴシゴシ力を当てて磨いたほうが良く汚れが落ちると考える人もいるかもしれません。でも実は、歯の表面の汚れを落とすのに力は必要なく、逆に力を入れて磨くことを続けていると、歯や歯茎の表面に傷をつけることによって悪影響を及ぼす恐れがあります。また、歯ブラシも早くダメにしてしまいます。
目安としては、歯ブラシを歯に当てた時に歯ブラシの毛先が広がらない程度を意識するとよいでしょう。
1-3歯ブラシを当てる場所
歯みがきをしている時、どこに毛先を当てるかあまり意識していない人も多いのではないでしょうか。ですが、どこを狙うかを意識するかそうでないかで、歯磨きの効果には雲泥の差が出てしまいます。
狙うポイントは3つ。
「奥歯の溝」「歯と歯茎の境目」「歯と歯の間」です。
この3つのポイントがきちんと磨けていれば、むし歯や歯周病のリスクをグンと減らすことができます。
歯と歯の間に関しては、歯ブラシだけでは限界がありますので、歯間ブラシやデンタルフロスも併用することをおすすめします。
1-4歯ブラシの動かし方
歯ブラシの動かし方もただ漠然と行うのではなく、「順番」「回数」を決めて」行うようにしましょう。そうしないと、磨けている場所とそうでない場所に偏りが出てしまうためです。
具体的には、「左下→右下→右上→左上」といった感じで磨く順番を決めて、1~2本ずつを丁寧に磨く感じで、1か所につき横方向に20往復、小刻みに歯ブラシを動かして徐々にスライドする感じでずらしていきましょう。歯ブラシを大きく動かすと、細かい部分に毛先が当たらなくなるので、磨き残しがでる原因になります。
なお、前歯の裏側や歯並びが悪い部分は、歯ブラシを横方向に動かしても当たりにくいため、必要に応じて縦方向に動かすなど、歯に毛先が当たるように工夫しましょう。
1-5歯ブラシをするタイミング
歯みがきの回数は、少なくとも1日に2回、できれば毎食後の3回行うようにしましょう。歯の健康にとってもっとも大事なタイミングは、夜寝る前の歯みがきです。
睡眠中は唾液の分泌が落ち、細菌が繁殖しやすい環境になってむし歯や歯周病のリスクが跳ね上がります。そのため、夜はじっくりと時間をかけて丁寧に磨くようにしましょう。
2.自分に合った歯ブラシの選び方

歯ブラシは人それぞれに合うものが違います。歯ブラシを選ぶ際には次のことを参考にして選んでみてください。
2-1大きさ
歯ブラシのヘッド(ブラシついている部分)の大きさは、あまり大きすぎるものはすみずみまで毛先が届きにくいため、おすすめしません。
歯や口が小さい人、細かい部分まで磨きたい、という方には小さめヘッドのものがおすすめですが、歯や口が大きめの人は普通~大きめサイズのものでもよいでしょう。
2-2毛先の形
毛先の形は、一般的には平らのものがおすすめですが、歯並びが悪い人や歯間に汚れが溜まりやすい人は山切りカットが合うこともあります。
毛先が極細になっているタイプのものは歯周病の方に向いていて、毛先が歯茎の中に入りこみやすいことで汚れをより効率的に掻きだしてくれます。
2-3毛の硬さ
歯ブラシの毛の硬さには「やわらかめ」「ふつう」「かため」があります。
使い分けとしては、
- やわらかめ・・歯茎に炎症を起こしている方、歯茎が弱い方、出血しやすい方
- ふつう・・一般的におすすめ。歯や歯茎にダメージを与えにくく、汚れ落ちも良い
- かため・・汚れ除去率が高い、タバコのヤニがつく方向け
といった感じで考えていただくとよいでしょう。
ただし、かための歯ブラシは、使いすぎると歯や歯茎にキズをつけ、歯にも着色しやすくなるため、頻繁な使用はおすすめしません。
2-4手動または電動
通常の歯ブラシのほかに、電動歯ブラシを使っている人もいるでしょう。
どちらにもそれぞれの良さがあり、電動歯ブラシにもいろいろなタイプのものがありますので、一概には言えませんが、電動歯ブラシを使う場合、普通の歯ブラシで正しい使い方ができていないと歯や歯茎を傷める恐れがあるので、注意しましょう。
3.歯ブラシの交換時期、どれくらいの頻度で交換する?目安は?

3-1歯ブラシの交換時期
歯ブラシの交換時期の大まかな目安は1カ月に1回程度です。これは見た目に問題がない場合でもためらわずに交換することをおすすめします。
その理由として、次のようなことが挙げられます。
◆ブラシにコシがなくなってしまう
見た目に変化がなくてもコシが失われると、汚れの除去効率が落ちてしまい、せっかく磨いたのに効果が半減してしまいます。
◆雑菌が繁殖してしまう
長期間使用した歯ブラシには雑菌が多く繁殖します。そのような歯ブラシを使って磨いても、雑菌を広げてしまうことにもなりかねないため、定期的な交換をおすすめします。
3-2毛先が広がった時
1カ月たっていなくても、毛先が広がっている場合には交換しましょう。そのまま使い続けていると、毛先が狙った部分に当たらなくなるため、汚れの除去効果が格段に落ちてしまい、むし歯や歯周病の予防効果が期待できなくなってしまいます。
また、歯茎に傷をつけて出血しやすくなったり、歯茎が下がって知覚過敏が起こったりする原因にもなります。
4.まとめ
歯磨きはやり方次第で効率を高め、むし歯や歯周病になりにくい状況を作り出すことが可能です。実際、歯科医師や歯科衛生士がむし歯や歯周病になりにくい大きな理由の一つとして、「歯磨きの正しい方法を熟知していて、実践しているから」ということが挙げられるでしょう。
また、歯ブラシの効果を最大限に引き出すためには、状態の良い歯ブラシ、自分に合った歯ブラシを使う、ということも忘れてはならないポイントです。
ついつい忘れがちな歯ブラシの交換タイミング。
歯の健康のためにも、毎月1回、決まった日に歯ブラシを交換する、と決めておくのもおすすめです。
今日からでも正しいブラッシング方法と適切な交換タイミングを意識し、「磨いているのに汚い」状態から脱却していつも清潔で健康な歯を保ちましょう!
この記事の監修者

こちらの記事もおすすめ!